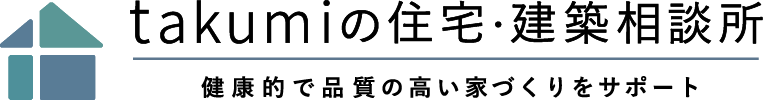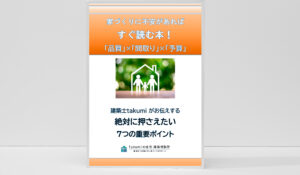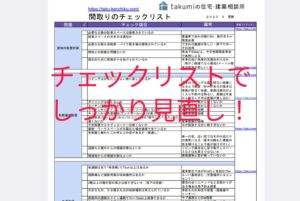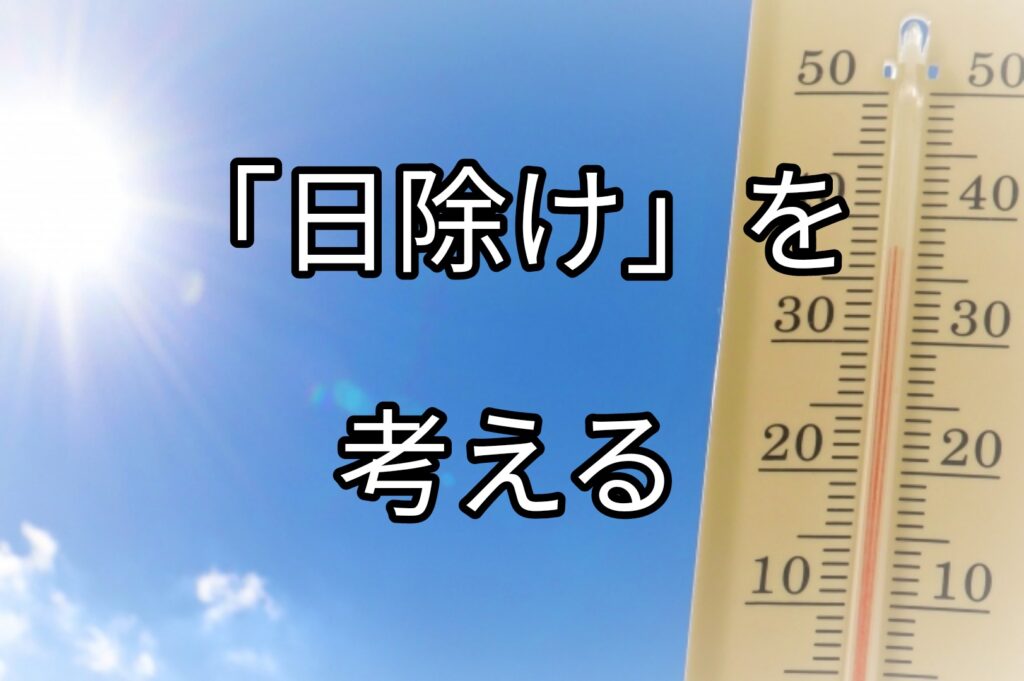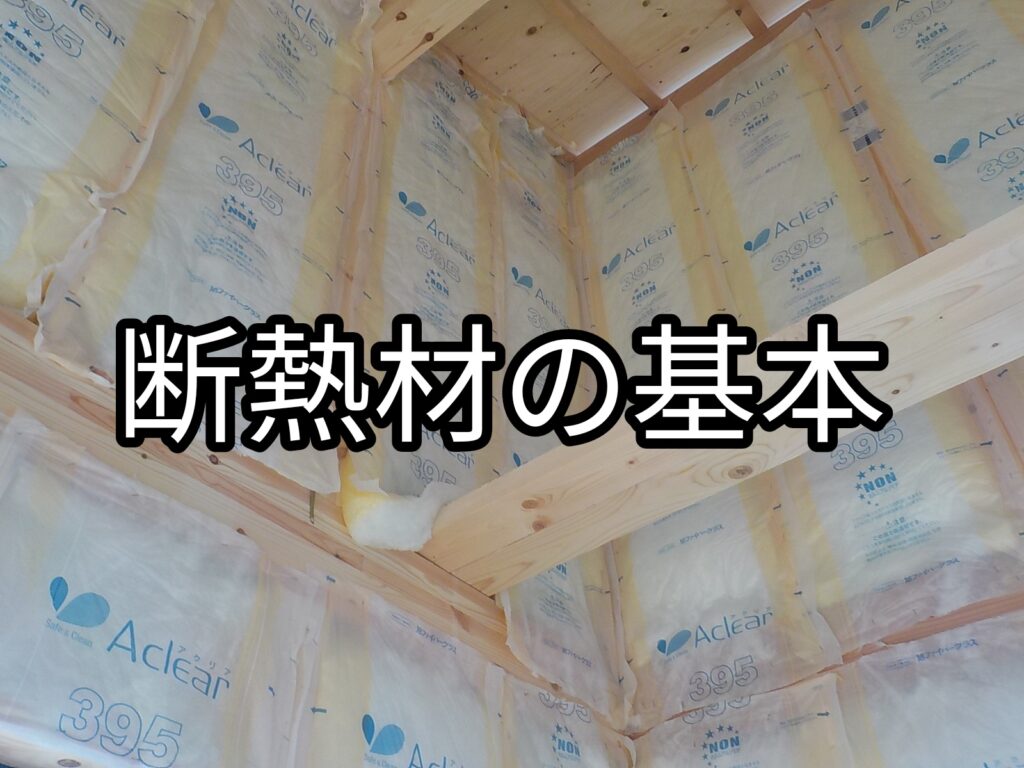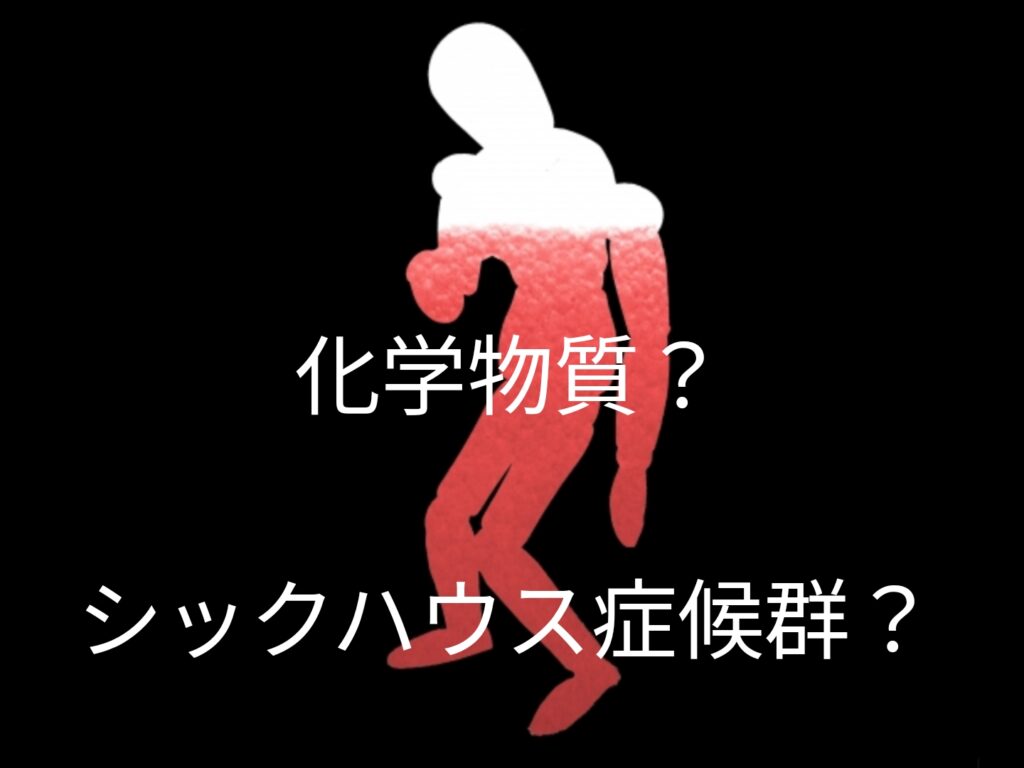
こんにちは!
一級建築士のtakumiです。
人が健康的に生活をする住まいに欠かせない要素はなにか。
明るさや風通し、動線の良さ、プライバシーと開放感のバランス、高い断熱性や気密性、もちろん安全のための耐震性能や施工の品質もあります。
しかし、実はあまり気にされない、、というか、気付かされていない日本の住宅の欠点、「化学物質」について解説したいと思います。
現在の日本の住宅
現在の日本の住宅、「低炭素」「ZEROエネルギー」など省エネ住宅への関心が大きく、高気密で高断熱の住宅がヨシとされています。
もちろんこれは正しいことではあり、断熱性能を高めることで室内の快適温度を保ち、気密性を高めることでさらに外気の影響を少なくし、熱交換型の第一種換気により、効率的に空気を入れ替えることななります。
ここで疑問。
なぜ、空気の入れ替えをするのか?
窓を締め切って部屋に人がいると二酸化炭素濃度も増え、空気の入れ替えは必要に感じます。
花粉症など外気に抵抗のある人以外、普通の感覚の人は、たまに窓を開けて空気の入れ替えをしたくなるもの。
実はそれだけではなく、機械換気による24時間換気は建築基準法で定められている義務なんですよね。
24時間換気は平成14年に施行されましたが、それまでに「シックハウス症候群」が全国的に問題になっており、建材や接着剤などの化学物質により、健康被害が多数報告されていました。
VOC(揮発性有機化合物)というものですね。
そのため、法整備をした訳ですが、ここには大きな問題がありました。
建築基準法で制限されたのは、ホルムアルデヒドとクロルピリホスだけで、ホルムアルデヒドについては使用料に制限をかけ、クロルピリホスについては全面的に禁止となったわけです。
そうです。ホルムアルデヒドでさえ、「多少」は入っていてOKなのです。
しかも、対象は建材だけで、施工に使う接着剤には特に制限はありません。
アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等といった化学物質には、なんの規制も無いのが現状なのです。
そのため、新築時の空気中の有害物質を除去するために、24時間換気が義務付けられ、微量な電力とはいえ、四六時中、換気扇を回し続けないと行けないという滑稽な法律になっているわけです。
ではなぜ、多くの化学物質に規制をかけないのか。
それは、国が大手ハウスメーカーや建材メーカーを守るため。要は利権がらみという訳です。
本当に健康を意識した法改正なら、まずはホルムアルデヒドとクロルピリホスだけでも、徐々に他の化学物質も規制をかけていき、将来的には健康被害の可能性のあるもの全てを規制することも可能な訳ですが、そんなことはせず利権を守り、24時間換気なんていう滑稽な方向に向かったということです。
24時間換気は、住宅の場合、換気能力は0.5(回/時間)以上であり、すなわち1時間で部屋の半分の空気を入れ替えるというものです。
ご自宅に24時間換気がある方はおわかりだと思いますが、ホント、微々たるもので、こんなものなら窓を開けた方がマシなシロモノです。
部屋に化学物質が充満しているのに、「徐々に空気を入れ替える」という、なんとも悠長な話です。
普通なら家中の窓を開け、風を通し、何度も空気を入れ替えることを試みるものでしょう。
さらに化学物質を閉じ込めてしまう日本の住宅
「高気密」な住宅というのも、実は問題を大きくしています。
気密性が高いから、断熱性能をさらに高め、効率的に部屋の空気を入れ替えられる、という論調な訳ですが、実際のところ、気密性が高いから化学物質が逃げる所もなく、0.5(回/時間)という微々たる能力の換気扇でしか出ていかないことになっています。
最近ではどこのハウスメーカーも工務店も競うように高気密も取り上げ、C値(cm²/m²)が0.5以下とか、0.4だとか、隙間の少なさを宣伝しています。
※建物全体の総隙間面積(平方cm)を床面積(平方m)で割る
単位は「cm²/m²」
そして、部屋の壁や天井の仕上げ材にはビニルクロスが使われています。
クロスには紙製や布製も存在はするのですが、扱いやすさや安さ、難燃性能、そして種類の多さから圧倒的にビニルクロスが主流です。
そう、ほとんどの方は「ビニール」の中で暮らしています。
床はどうかと言うと、多くはフローリングとなっていますね。
フローリングも無垢材なら良いのですが、これまた「複合フローリング」と言って合板を接着剤で張り合わせ表面には薄い天然の木材やプリント柄を施したものがほとんどです。
このように、隙間を極力なくした空間で、壁や天井はビニール、接着剤で床は貼り合わせた合板、という組み合わせの住宅で生活する方がとても多いということになります。
そして極めつけは、「窓の少なさ」「窓の小ささ」です。
窓というのは一般的には外壁よりも断熱性能が小さく、断熱性能を高めるには窓の割合を小さくするのは正解です。
耐震的にも窓といった「開口部」は少ない方が有利になるのは事実です。
そのため、極力、窓を小さく、少なめにする方が増えているのも事実です。
部屋内に化学物質が充満していることに気づき、いざ、自然換気をするとなっても、換気能力が小さく、うまく有害物質が出ていかないという原因になります。
可能な限り自然素材を使う
では、室内の化学物質を少なくするために、どのような方法があるのでしょう。
まずは、部屋の表面にある壁や天井、床材を見直すことです。
壁や天井の仕上げ材
ビニルクロスには表面の塩化ビニールの他、可塑剤や安定剤、難燃剤、防カビ剤、発泡剤が含まれ、そして接着剤にも有害な化学物質が含まれています。
壁や天井の仕上げは、一般的にはビニルクロスが主流であり、コストを抑えるにはとても良い選択肢ではあります。
しかし、化学物質が含まれており、絶えずVOCを放出しているという現実があります。
また、「ビニール」という性質上、部屋の中に浮遊している湿気や有害物質を吸収することも無く、部屋の中に閉じ込めてしまう側面もあるのが現実です。
壁紙クロスの材料には、布クロスや紙クロスも存在します。
ビニルクロスに比べて、多少は湿気や臭気を吸収するかもしませんが、コスト的にはビニルクロスの倍以上するものが多く、どちみち接着剤も使いますので、化学物質が含有する可能性が残ります。
壁や天井には、調湿作用がある自然由来の材料がおすすめで、中でも漆喰や珪藻土といった材料が調湿には優れています。

※調湿作用と言っても、実際には高い湿度の際に湿気を吸収する能力は高いが、冬場の乾燥した空気に湿気を含ませるような機能はそれほど期待はできないのが事実。
漆喰の主成分である消石灰には、ホルムアルデヒドなどのVOCを吸収する性質があります。
そして、消石灰にはアルカリ成分により、ホルムアルデヒドを分解し無害化する能力があるのも大きな利点です。
同じような材料に、珪藻土というものもあり、こちらは藻類の一種である珪藻の殻の化石でできており、二酸化ケイ素(SiO2)を主成分としています。
珪藻土も漆喰と同じくVOCを吸収してくれる性質があります。
注意が必要なのはこれら漆喰や珪藻土の材料の中にも化学物質が含まれる可能性があるということです。
漆喰は、消石灰そのものに硬化する成分がありますので、海藻糊(ノリ)や麻・藁などの植物繊維(スサ)の他には化学物質を混ぜなくても漆喰として機能します。(中には取り扱いやすいように、化学物質混ぜたものがあるので要注意。)
一方、珪藻土にはそれ自体に硬化する機能はないので、セメントや合成樹脂が含まれることが多いので、完全な自然由来の材料は少ないようであり、注意が必要です。
床材
複合フローリングには、構成する合板やMDFを接着する接着剤、表面をコーティングする塗料、フローリングを下地に接着する接着剤に化学物質が含まれています。
フローリングの材料としては、無垢材を使用するのが第一です。
無垢フローリングは木材本来の香りや質感も楽しめ、素足で歩くとより一層気持ちの良いものです。

無垢フローリングにも大きくわけて広葉樹と針葉樹があり、様々な樹種がありますので、その選択も楽しみの一つとなるでしょう。
※無垢フローリングについてはこちらのブログもご覧下さい。
↓↓↓
マイホームの計画は「床材」にこだわりを!~無垢フローリング材おすすめ10選!~
注意すべきは、張り付けに使用する接着剤です。
フローリングは接着剤とフロアネイル(細い釘)で固定しますが、接着剤には「低VOC」のものもありますが、化学物質がゼロというのはなかなか難しいかもしれません。
しかし可能な限り化学物質を抑えた水性の低VOCの接着剤や、自然由来の接着剤もありますので、できるだけ化学物質を避けたものを使用してもらいましょう。
畳
実は、畳も化学物質の危険性があります。
現代の畳の中には藁の代わりに発泡スチロールや合板を芯材として使用することがあり、これらを接着する接着剤は化学物質を含んでいます。
また、畳の芯材(藁や木材)やイグサを虫害やカビから守るために、防虫剤や防腐剤も使用されることがあります。
そのほか、染料や仕上げ剤、難燃剤も使われることがあります。

畳は日本の文化であり、昔からの自然素材による畳には、イグサや藁による調湿効果があり、イグサの香りによるリラックス効果も有します。
またイグサの柔らかさと藁の弾力性は足裏にも優しく、「畳に寝転がる」ことの気持ちよさも格別です。
そして、イグサには二酸化窒素(NO₂)やホルムアルデヒドなどの有害物質を吸着する能力もあります。
畳の部屋、コーナーを作る際には、畳は昔からの材料である、イグサ(畳表)、藁(畳床)、畳縁(麻や木綿)を使った本物の畳を使うことをおすすめします。
断熱材
壁の中にある断熱材にも、化学物質を含むものが多くあります。
グラスウールは、ガラス繊維を結束するためのフェノール樹脂やユリア樹脂にホルムアルデヒドが含まれる場合があります。
そして、グラスウールの欠点は職人(大工)がどこまで丁寧に施工できるかにより品質に大きな差が生まれること。
柱等の金物や筋交いの裏に「隙間ができやすい」こと、また湿気を含みやすいことも大きなデメリットです。
湿気ったグラスウールは断熱性能が大きく落ち、さらに壁内結露やカビといった不衛生な状態に陥りやすい性質があります。
ウレタンフォーム(吹き付け)は断熱性能も高く、そして隙間なく施工できるメリットがありますが、デメリットとしては、ウレタンの製造に使用する揮発性があるイソシアネートや、発泡剤であるガスも有毒性があることです。
断熱材にも自然由来の材料が存在します。
ひとつはセルロースファイバーという素材です。
セルロースファイバーは、新聞紙等の古紙よ再生紙を原料とし、繊維状に加工した紙を壁や天井に吹き付ける工法です。
髪が主原料のため燃えやすい性質を補うため、難燃処理をする必要があります。
その難燃剤としてホウ酸処理しているものは毒性も少なく、防虫効果もあり、現在使われることが徐々に増えている材料です。
また、紙が主原料ですので調湿効果もあります。
もうひとつ、ウールブレスという羊毛を原料とした断熱材があります。
ウールブレスも自然由来の素材ですので、毒性もなく、また難燃処理もホウ酸使ったものは同様に防虫効果もあるということです。
ウールブレスの欠点は、コストがやや高めということと、グラスウール同様に湿気にやや弱いことです。
また羊毛ですので防虫処理も必要となり、これに化学物質が使われることがあるので注意が必要です。
まれに羊毛アレルギーの方もおられますので、アレルギー持ちの方には当然、不向きとなります。
自然素材の断熱材としては、今のところ、ホウ酸処理をしたセルロースファイバーが最も適していると考えます。
壁や天井の下地である石膏ボード
壁や天井の仕上げ材の後ろには、ほとんどの場合、石膏ボードが使われています。
実はこの石膏ボードも化学物質が使われているものが殆どなのです。
シンプルな石膏ボードでも、石膏を固めるために接着剤や硬化剤、防カビ剤などが使われ、ホルムアルデヒド等、多少なりとも化学物質が含まれているといてます。
さらに強化性、耐水性、難燃性など性能を付加すると化学物質も増えていくということになります。
最近は石膏ボードの代わりになる無添加に近い材料もありますが、コスト面ではなかなか石膏ボードには勝てず、採用するには難しい面もあります。
コスト面で無添加のボードを使うことが出来れば良いのですが、それが難しい場合にはできるだけシンプル(耐火性や防水性などの無い)な石膏ボードを使うことです。
防腐防蟻処理
木造の建物は建築基準法により、地面から1mまでは防腐防蟻処理を行う必要があります。
この防腐防蟻処理の薬剤はかつてはクロルピリホスという毒性の強いものが使われていましたが、現在ではクロルピリホスは使用禁止になり、主流は合成ピレスロイド系薬剤、ネオニコチノイド系薬剤など農薬系の薬剤があります。
合成ピレスロイド系薬剤は即効性、持続性があり効果が高いのですが、揮発性があり、アレルギーを起こしたり呼吸器系への影響など健康面への悪影響が懸念され、微量でも長期間の暴露で神経系への影響が議論されています。
ネオニコチノイド系薬剤は比較的安全とされながらも、長期間の暴露で神経系への影響が議論されており、特に子供や妊婦への影響を懸念する研究もあります。
ミツバチや他の有益な昆虫に悪影響を及ぼすことが知られており、農薬としての使用が一部の国で規制されています。
これら農薬系の薬剤に対して、防腐防蟻処理剤にも自然由来のホウ酸があります。
天然鉱物(ホウ砂など)から精製され、自然界に存在するものです。
防腐剤、防蟻剤、殺菌剤として建築や工業で使用されるほか、医療や化粧品にも使われています。
ホウ酸は揮発性が小さく、シックハウス症候群のリスクが少ないこと、また哺乳類への毒性が低く、適切な濃度で使用すれば人体への影響はほぼありません。
また、環境面でもホウ酸は分解されやすく、土壌や水系への長期的な汚染も少ないとされています。
まとめ
日本の住宅というのは、実は化学物質にまみれている、ということが分かりますね。
もちろん、昔の日本家屋はこうではありませんでした。
これは、日本の高度成期に大量生産が主流となり、住宅が工業製品化していったことが背景にあります。
また、平成14年の建築基準法改正においても、ホルムアルデヒドとクロルピリホスしか規制の対象にならず、他の化学物質が放置され続けているのは、それらを売る大手企業やハウスメーカーの利権を守っていることにほかなりません。
ハウスメーカーの担当に確認しても、「大丈夫です」「健康被害がない少量です」「建築基準法をクリアしたフォースターです」といった回答しかできないでしょう。
こうした建材の問題に気づき、健康面に留意した材料を使用している工務店さんも少数ではありますが存在します。
安さ、流行り、デザイン、間取り、高気密、この辺りも大事ではあるのですが、あまり囚われすぎないようにし、安全面を第一に考え、耐震性と共に「健康」もしっかり考えて、業者選びをするようにしたいものです。