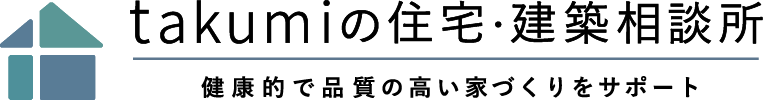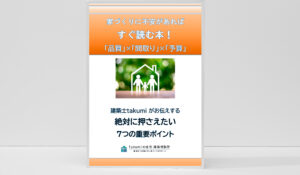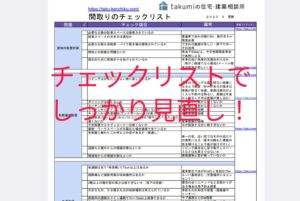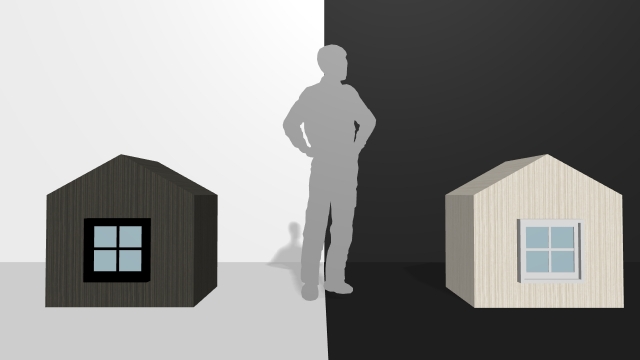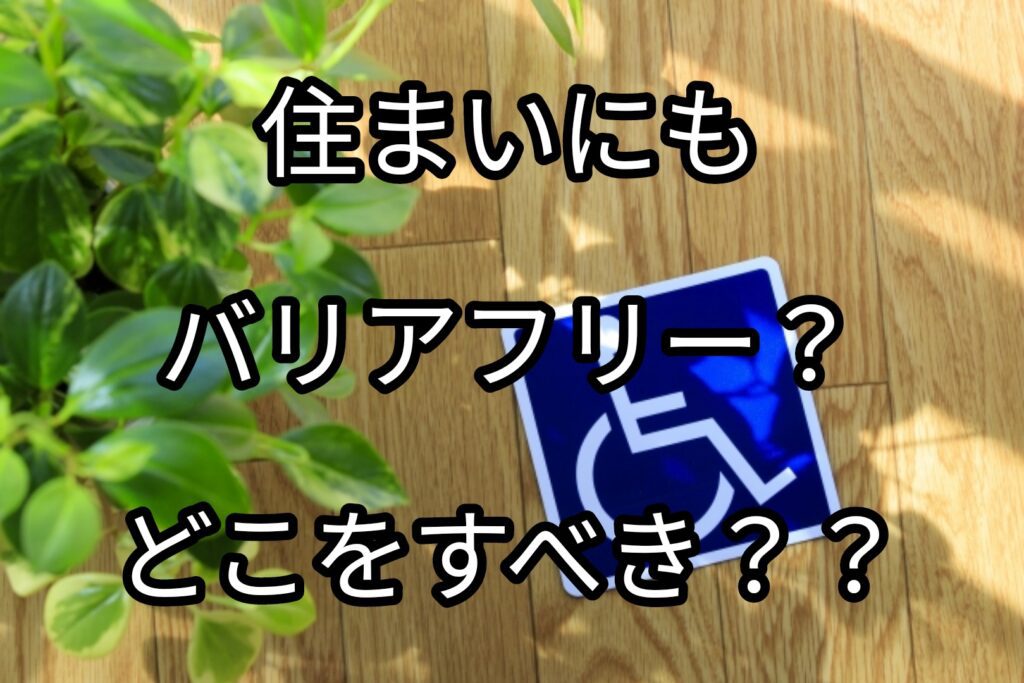こんにちは。
一級建築士のtakumiです。
工事において品質管理が重要なのは当然なのですが、多くは見えない部分に大事なチェックポイントが多いものです。
特に、鉄筋、コンクリート、木材、鉄骨といった「構造部材」は、品質が命です。
正しい材料で、正確な工事をしないと、「施工不良」や「欠陥」といった最悪な結果になってしまいます。
重要なチェックは、見えなくなる前に確認する必要があり、工事をする業者(施工者)は、このような「不可視部分」を写真に納めておく必要があります。
「工事写真」というものですね。
戸建て住宅の工事では、工事写真をきちんと撮影している業者も少なく、依頼しておかないとそのような証拠を残してくれません。
工事では、きちんと行った「証拠」をもらうように、業者に相談しておきましょう。
以下は不可視となる部分の品質管理における一例です。
地盤の確認は超重要!
地盤がしっかりしていないと、いくら建物が頑丈でも地震で地盤が沈下してしまって、地震後に建物が使えなくなることがあります。
建物の検討の際には、安全な地盤であるかどうかを確かめる必要があります。(前もって、地盤調査が必要。)
固い地盤であればそのまま基礎を乗せられますので、工事で土を掘る際に地盤の状態を確認します。
地盤が弱い場合には、地盤改良や杭を打って、必要な耐力が得られるように工事をします。
そして、杭や地盤改良が不要な場合は、基礎の下は必要以上に掘ってはいけません。
基礎が乗ってくる地盤面が硬いままの状態を保たなければならないため、余分に掘り下げてはいけないわけですね。
防湿シートは敷設すべし!
地盤は常時、湿気を含んでいますので、建物の一番下に防湿シートを敷設します。
地中からは、絶えず湿気が上がってきますので、建物の下部全面に、必ず防湿シートを施工しておく必要があります。

基礎の構造確認
基礎工事では、基礎の寸法、鉄筋の径や本数、コンクリートの強度などの品質を確認する必要があります。

また、コンクリートは型枠内に放り込んだだけでは空洞だらけになりますので、バイブレーター等によって密実にする必要があります。
コンクリートにできてしまう空洞は、「まめ」とか「じゃんか」といい、その部分的が「密実では無い」ためにコンクリートが負担すべき圧縮力が見込めなくなり、品質が悪くなっていることになります。
防蟻処理、防腐処理は必要か?
地面から1m以内の土台や柱などの構造材には、防腐や必要に応じて防蟻措置が必要とされています。
シロアリなどの害虫や湿気による老朽化を防ぐ措置です。
設計されている塗布や処理方法がなされているか確認をします。
また、耐久性に優れた木材(ヒノキやヒバなど)もありますので、各メーカーによって体に影響の少ない工法も開発されており、対策がなされていれば必ずしも薬剤は必要ではない措置といえます。
アンカーボルト、ホールダウン金物、接合金物が適正に付けられているか?
各金物がきちんと取り付けされていないと、地震などの水平力を受けたときに、構造部材が本来の耐力を発揮できません。
そうなると柱や梁の接続部で壊れてしまい、「全壊」や「半壊」となるケースがあります。
特に、柱の引き抜き力に対抗する金物は、その柱が受ける引き抜き力に応じてホールダウン金物の他、いろんな種類があります。
これらが間違っていないか、正しく取り付けられているかの確認が重要です。
筋交いや耐力壁の配置、火打ち梁は適切か?
筋交いをはじめ、耐力壁は構造の命です。
適切な配置で適切に取り付けられていないと耐力を発揮できません。
筋交いであれば上記の取り付け金物が適正か、耐力壁は倍率通りのものか、取り付け方法は適切か、大きく欠損する設計になっていないか、といったことはチェックが必要です。
また、梁や土台の隅に変形防止として火打梁を入れます。

構造の基本は三角形ですからね。
建物の隅はもちろんのこと、歪な形の場合や大きな吹き抜けのある場合は建物の形状に応じて火打梁の検討が必要になります。
下地材(手すり、据付家具、カーテンレールなど)
木工事(大工さんの工事)が終わる前に、下地材の確認が必要です。
内装を貼ってからでもボードの上からコンコンたたけば下地材の存在は分かりますが、できる限り見ておきたいですね。
手すりの取り付けは階段は当然ですが、トイレや玄関にも取り付けることが多いですね。
エアコンやカーテンレール、ブラインド、そのほか据付家具にも下地材必要な場合があります。
屋根
屋根はシンプルな形でないと雨漏りの原因になることがあります。
形は設計で決まっているので工事のチェックではなんともなりませんが、複雑な形であれば徹底チェックが必要です。
まず当たり前ですがシーリングに頼るような設計、納まりはダメです!
これは屋根では少ないですが外壁ではアリがちなことです。
シーリングはあくまでも二次的な防水方法ですので、10年も経たないうちにその性能が低下してきます。
屋根に「谷」や「入隅」がある計画は雨が入りやすい構造ですので、見直すことが出来れば見直した方が無難です。
見直しが出来なければ、施工図、詳細図か半永久的に雨漏りがしない構造、おさまりになっているか、検証が必要です。
また、最近ではデザイン重視で軒の出がほとんどない設計も多いのですが、屋根と外壁の間へ雨が入り込みやすいため、雨漏りの原因になります。
外壁の下地(防水紙)
外壁はサイディングがほとんどですが、サイディングの下には必ず防水紙といった下地が必要です。
サイディングだけでも防水効果はありますが、継ぎ目や端部から雨がしみ入ることはよくあります。
そのため、この防水紙がしっかり貼られていないと雨漏りのリスクがかなり高まることになります。

断熱材がちゃんと入っているか?
断熱材はどんな等級であろうが建物をすっぽり覆うように全体に必要です。
外壁、1階床、最上階の天井(もしくは屋根)です。

断熱材が施工されていない部分があったり、大きな隙間ががあると、そこから結露したりカビたりと、問題の原因になることが多いのです。
まとめ
住まいの品質というのは、このように隠れてしまうところがとても重要です。
手抜き工事や欠陥住宅というのは、このような見えなくなる部分に多くのミス、不具合が隠れているものです。
大切な家づくり。見た目だけでなく、見えない品質を重要視している業者に依頼するように心がけましょう。
※建物のチェックをする「工事監理」に関する記事はこちらです↓↓↓
工事監理の重要性~注文住宅の手抜き工事や瑕疵といった不安を無くす役割~
※takumiのnote記事でも、家づくりのブログ記事をアップしていますので、是非お読みください↓↓↓